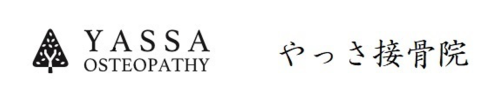フルクラム・オステオパシー・スタディ・グループ(通称:FOSG)在籍
勉強会、復習会、小グループによる研修など年間約200時間ほど現在も研鑽中。国内においてオステオパシーの正式な国家資格や学校認可がない背景がある中、それでも海外講師との繋がりや習ったことを大事にしそれぞれが研鑽しながら学び続けていくグループ。
テクニックセミナーが多い国内において、もっと大事な自然法則や基礎的な概念など、先人のオステオパスの先生達が伝えたかったことを丁寧に整理しながら、臨床に生かせるように研鑽してオステオパスとして成長していくことを大事しているグループです。
解剖学と個体発生論4(Homunculus Interni)2024年1月
講師 Jean-Paul Hoppner D.O. MRO
解剖学と個体発生論3( Homunculus viscerocranii)2023年7月
講師 Jean-Paul Hoppner D.O. MRO
解剖学と個体発生論2( Homunculus Neurocranii)2023年1月
講師 Jean-Paul Hoppner D.O. MRO
解剖学と個体発生論1(Basic Fundamentals of Metabolic fields)2022年8月
講師 Jean-Paul Hoppner D.O. MRO
ベルギー在住の先生ですがドイツ語、英語、ラテン語などにおいても精通していらっしゃるので、E.Blechschmidt(ブレヒシュミット)教授の⽂献を原語で読み正確に理解することができる先生です。E.Blechschmidt(ブレヒシュミット)教授の動きのある形態学の研究や解剖学の探究、さらにA.T. スティル博⼠の書籍を徹底して読み込んでいるヘップナー先生からの講義は、これからオステオパスとして成長していくのに必要な過程をたくさん教わりました。
そして2022年から2024年にかけて本講義とFOSGのメンバーや受講生内で復習会等しながら、組織や器官の発達の概念の整理とディスカッションを続けています。講義を受けて終わりではなく、自分たちが取り入れる組織の概念自体が新しいので理解に誤解が生じないように講義を受けた者同士で時間をかけて整理してきました。この講義を受けたことによって、形態というものの考え方や解剖学の臨床への活かし方が大きく変わりました。また組織学や発生学それに伴う発達の原理と法則が臨床において非常に重要で、『症状=このテクニック』ということでなく本来患者さんに治療すべきものが何なのかというものがしっかり理解できた講義でした。
慢性的な激しい痛みに対するオステオパシー治療 2019年11月
講師 フィリップ・ドゥリュエルD.O. Philippe Druelle D.O.
考えること、感じることのできるオステオパスの手 2019年8月
講師 ジュリー・マイ D.O. (Julie Mai D.O.)
エナジェティック・インパルス2 2018年11月
講師 フィリップ・ドゥリュエルD.O. Philippe Druelle D.O.
オステオパシーにおける産科学と周産期 2018年8月
講師 アン=ジュリー・モラン D.O. (Anne-Julie Morand D.O. )
セントラルチェーンと自己調節 第2部 2018年5月
講師 フィリップ・ドゥリュエルD.O. Philippe Druelle D.O.
エナジェティック・インパルス 2017年11月
講師 フィリップ・ドゥリュエルD.O. Philippe Druelle D.O.
セントラルチェーンと自己調節 2017年5月
講師 フィリップ・ドゥリュエルD.O. Philippe Druelle D.O.
ムーブメント・オブ・ライフとバイオダイナミック・フォース 2016年11月
講師 フィリップ・ドゥリュエルD.O. Philippe Druelle D.O.